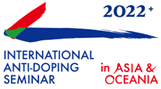アジア・オセアニア国際アンチ・ドーピングセミナー 2022+
Organised by

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)は、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)との連携のもと、スポーツ庁主催「アジア・オセアニア国際アンチ・ドーピングセミナー 2022+」を2022年12月14日・15日に開催しました。
今回で16回目を迎えた国際セミナーには、東京とオンラインの両方で200名以上の参加者が集まり、「Reuniting the Clean Sport Community: with a Living Legacy to Preserve the Values of Sport(クリーンスポーツコミュニティ再結束:スポーツの価値を守るための生きたレガシーとともに )」をテーマに、クリーンなスポーツ環境を作るための効果的なプログラムの実施や最新のルール等について情報交換しました。新型コロナの影響により各国アンチ・ドーピング機関(NADO)や各地域アンチ・ドーピング機関(RADO)が東京に集まっての開催は3年ぶりとなります。
ハイブリッドセッションは、アジア地域のWADA執行委員である井出庸生文科副大臣による挨拶により開幕しました。続いて、WADA会長Witold Bańka氏は、クリーンスポーツコミュニティが、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の実現においていかにレジリエンスを発揮したか、世界的なPLAY TRUEムーブメントにおいてTokyo2020レガシープロジェクト「PLAY TRUE 2020、Sport for Tomorrow」が重要であったかを振り返りました。
2日間を通して、アジアとオセアニア地域からの参加者は、それぞれのプログラムをより良くするための方策について学び・共有し、セミナー終了後には東南アジアのアンチ・ドーピング機関(SEARADO)とJADAによる、セミナーの内容を振り返るためのワークショップが開催されました。
後援:
・外務省
・独立行政法人日本スポーツ振興センター Sport for Tomorrow
・International Testing Agency (ITA)
・International Paralympic Committee (IPC)
・Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO)
AM
TOKYO
クリーンスポーツコミュニティ再集結:
スポーツの価値を守るための生きたレガシーとともに



WADA Compliance, Rules and Standards副部長Kevin Haynes氏は、Code Compliance Questionnaire (CCQ:世界規程に対する遵守状況を署名当事者に確認する質問票)の傾向と分析、およびアンチ・ドーピング機関(ADOs)がより良い実践を行うための方法について説明しました。2021年1月から施行された「教育に関する国際基準 (ISE)」に基づき初めてのCCQが行われたことで、教育の体制・推進状況を客観的に把握することが可能となったとし、アジア地域における教育分野への予算配分が世界をリードしているという分析を示しました。Tier3およびTier4のADOsに対する、今後のCCQに向けてのヒントも示唆しました。
Tim Rickets氏は、検査に関してCCQでの不適合事項等に基づき、世界の検査の体制や状況を評価しました。 2023年1月に施行される「検査及びドーピング調査に関する国際基準 (ISTI)」の主要な変更点と、乾燥血液スポット検査(DBS)の導入などについても説明しました。
JADA専務理事・浅川は、JADAの体制を共有し、国際基準に即した規律パネルに焦点を当てながら、その組織的/運営上の独立性について説明しました。
ノルウェー・アンチ・ドーピング機関 (ADNO) のInternational Relations and MedicalディレクターMartin Holmlund Lauesen氏は、CCQへの回答プロセスを振り返り、各国アンチ・ドーピング機関が今後どのように対処すべきかを説明しました。「CCQに対して神経質になりすぎず、チームを組んで対応すべきである」というLauesen氏からのメッセージを受け、今後対応していくアンチ・ドーピング機関からの実践的な質問が投げかけられました。
PM
Hybrid
未来に向けたクリーンスポーツコミュニティの再結束:
すべてはPLAY TRUE Creatorのために





WADA会長Witold Bańka氏は、キーノートスピーチにおいて、スポーツ庁やJADAがWADAとの連携のもとセミナーを開催することの意義を述べました。また、本セミナーを通して、参加者同士が実践的な知見を共有し、学び合いのネットワークを構築することで、自組織でのクリーンスポーツを推進するためのリーダーとなることへの期待を述べました。さらに、“playground to podium(遊び場から表彰台へ)”の表現で、パスウェイに即した教育の重要性を強調しました。
「アスリートクロストーク」では、スポーツ庁長官・室伏広治氏、WADA副会長・YangYang氏、ニュージーランド・アンチ・ドーピング機関のアスリート委員Portia Bing氏 が登壇しました。各パネリストよりそれぞれのアンチ・ドーピング機関においてロールモデルアスリートとしてどのような経験を積んでいるか、学んだ教訓、メッセージなどが共有されました。室伏広治氏は、オリンピック選手である父親から、どんな約束事や事象に対しても誠実に対応することの大切さを学んだと述べました。Bing氏は、アスリート自身やサポートスタッフが「アンチ・ドーピングについて学び発信することは、安全な職務環境を用意することと同意」といった視点で、アスリートが安全なスポーツ環境づくりに貢献できる可能性を強調しました。Yang Yang氏は、WADAのガバナンス改革によりWADAアスリートカウンシルが始まることに伴い、アスリートが代表権を持ちクリーンスポーツ環境を創っていく過程にどのように関わっていくことができるのか、という点も含め解説しました。パネリスト3名ともアンチ・ドーピング機関とのかかわりをそれぞれ持ち、自身の活動を通してインフルエンサーになっていることを踏まえ、クリーンスポーツの実践者たちに対して、アスリートはクリーンで偽りのないスポーツに対して情熱を持っていることを改めて伝えました。そして、アンチ・ドーピング機関が共通のゴールに向かう過程で困難があったとしても、情熱を持ちアスリートに継続的にアプロ―チしていく方策の提案がありました。
WADA事務局長Olivier Niggli氏は、外部意見等を取り入れた6年間の準備期間を経て、2023年から開始されるWADAのガバナンス改革について説明しました。WADAはNADO/RADO、IF、ITA、iNADOなどのステークホルダーと協力してWADAの機能を高めるための活動を行い、協力関係を基にして各種のプログラムの推進、質向上に対してガイダンスを行っている点を強調しました。特に、有意義なアスリートのエンゲージメントの促進を図っていくことが改革の中核としつつ、WADAの意思決定機関である執行委員会 (Executive Committee)と理事会 (Foundation Board) へのアスリートの代表権の追加についても触れられました。韓国・釜山で開催される「第6回2025 World Conference on Doping in Sport」では、2027年版世界アンチ・ドーピング規程の改訂内容が承認される予定でいることが説明されました。
WADA教育委員会の山本やや委員は、2022年9月シドニーで開催された「Global Education Conference」での成果について話しました。Bańka会長が冒頭で強調した“catch and punish (検査により違反者を特定し制裁を課す)”と “support and prevent (サポートと予防)” のバランスを保ったアンチ・ドーピング・プログラム推進の重要性の考え方を、「すべてのアスリートは、スポーツを始めた時はクリーンな状態で始めていることが前提としてある。ISEではアスリートがそのキャリアを通じてクリーンで誠実であり続けられるように、アンチ・ドーピング機関が価値観の醸成にアプローチしていくことを求めている」と説明しました。アンチ・ドーピング機関がお互いにグッドプラクティスや課題を学び合い、各地域に即した履行方法を見出すことが実効性を高めることにつながると述べました。
AM
TOKYO
すべての人にクリーンなスポーツ環境を:質の高い実践のためにCCQの経験を共有し、協働して向上していく

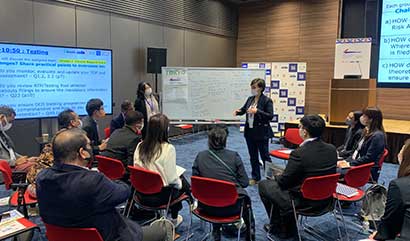

ワークショップA:検査
WADAのTim Ricketts氏が、ISTIで要請されている事項を再確認し、それらの要請事項に即したCCQの質問を確認しました。JADA検査部・飯塚より、JADAが検査員 (DCO)の採用と育成、研修の内容をCCQの質問に即して改定をしてきたプロセスを共有しました。東南アジアアンチ・ドーピング機関(SEARADO) Gobinathan Nair事務局長は、東南アジア地域において検査関連の人材育成を長期的な観点で行い、持続可能性を高めていること、地域内での学びを促進することで、徐々に国際標準に合わせた考え方を変化させ、適材適所の考え方にシフトしていくことの重要性について発表しました。各グループでは、下記のトピックについてディスカッションしました。
| 1) | どのようにリスクアセスメントを基に検査を計画し、モニター・評価・更新するか | |
| 2) | どのようなアプローチによりRTP/検査対象プールアスリートの居場所情報のモニタリングを行い、必須とされている情報の提出を担保するか | |
| 3) | DCOのトレーニングプログラムが理論的で、実践にも活きる総合的な内容が含まれた研修であるか、DCOの定着度をいかにモニタリングするか |
ワークショップB:教育
ISEが施行されて初めてのCCQで、「検査の前に教育」や「競技大会の前の教育」といったISEの原則を各アンチ・ドーピング機関が体制としていかに構築することができるかディスカッションがされました。まずJADA教育部部長・山本より、“playground to podium(遊び場から表彰台へ)”の考え方を実現するために「クリーンスポーツ教育パスウェイ」を構築していくため、日本国内での教育体制の整備、各関係機関との連携を図っていることを説明しました。長期的な観点から持続可能な体制を創っていくことが、クリーンスポーツ環境を創ることにつながっていくと強調しました。中央アジア・アンチ・ドーピング機関 (RADOCA) Maira Bakasheva会長からは、メンバー国が教育計画を策定するため、覚書を締結しているJADAからの支援を下に取り組んだことが、理解促進につながったことや今後の取組方法について説明がありました。グループディスカッションでは、ISEにおける最低要件の履行のみならず、最低要件を超えてより良い実践にどのようにつなげることができるか意見を出し合いました。
| 1) | 教育対象プールの設定方法や学習目標の設定の仕方 | |
| 2) | Educatorに求めるコンピテンシーの設定の仕方を含めたEducator育成のプログラムをどのようなものにするか | |
| 3) | 「アスリートのアンチ・ドーピングのはじめての経験が教育となるように」というISEの原則をいかに実現していくか |
PM
Hybrid
すべての人にとってのクリーンスポーツ環境:2021年世界アンチ・ドーピング規程および国際基準への対応


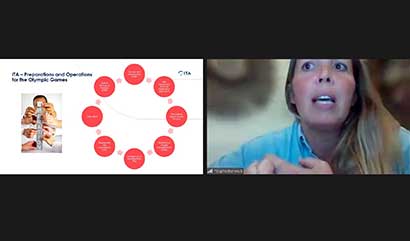


WADAアジア・オセアニアWADA Kevin Haynes 氏は、CCQが開始されてからの7年間を「私たちが現時点で知っていること (what we know so far)」と「私たちが知らないこと (what we don’t know)」として説明し、コンプライアンス・モニタリング・プログラムの因果関係の分析や是正措置 (Corrective Actions)の複雑さ、モニタリングから得られたデータ分析結果の利用可能性、主要な分野の定期的な監査・審査など、WADAの今後の展望を説明しました。
「コンプライアンスを通した成熟 (Compliance Maturity)」は、すべてのADOのキーワードとして強調しました。アンチ・ドーピング・プログラムの質を向上させるため、各組織や業務過程においてコンプライアンスの観点を踏まえた実施が通常業務として浸透し、各機関・実務家が自己評価と自己修正を行っていくことが狙いとしてある、ということを再確認しました。
WADA General Counsel・Ross Wenzel氏より、2021Codeの下での制裁や聴聞会のケースが共有され、そこから見えてきた課題等に関するプレゼンテーションが行われました。非特定物質に起因する違反が疑われたケースについて、サプリメント使用により体内侵入経路の立証をアスリートが求められている点について述べました。また、「柔軟性と厳格化」の両輪でCodeが変遷してきていることを説明しました。実際の事例から学ぶことを通して、各アンチ・ドーピング機関がアンチ・ドーピング・プログラムをより効果的に展開していくことができるとしました。
2024パリ大会に向けてアンチ・ドーピング・プログラムがすでに動き始めている旨が、ITA (国際検査機関)Sophie Berwick氏から共有されました。検査プログラムは「検出」の観点からは重要ではあるが、JADAが東京2020大会の際に取り組んだPLAY TRUE 2020のように、継続的な教育や価値の発信が大会をクリーンにするためにはさらに重要であると述べました。また、各ステークホルダーが協力し、資源を最適化してプログラムを実施していく必要があると強調しました。
JADA教育部・堀からは、「生きたレガシー」としてのPLAY TRUE 2020プロジェクトの継続実施内容について紹介しました。持続可能なスポーツの未来を実現させるため、世界中の子どもたちやアスリートがスポーツの価値を共有する「SPORT & ART」 の取り組みを、東京2020大会後も継続していることを説明しました。また、アジア・オセアニア地域のアンチ・ドーピング機関やその他各国のスポーツ関係者らに対して、「リアルチャンピオン教育パッケージ」の提供も含めた教育プログラムの構築支援についても説明しました。
SEARADO x JADA ジョイントワークショップ

SEARADOとJADAは覚書を通して8年間に渡るパートナーシップを構築しており、コロナ禍で行うことができなかったお互いのプログラム実施の進捗状況を確認し合いました。ワークショップでは特に、「運営上の独立性」と「教育」の重要なトピックスについて、JADAによるプログラムの実地体験も含めながら、SEARADO加盟国メンバーがそれぞれの国での改善点を自身で洗い出し、アクションポイントを明示化しました。SEARADO Gobi Nair事務局長は、「ワークショップはとても楽しく充実していた。セミナーでの学びを振り返りつつ、東南アジア地域での実践につなげられるとても良い機会になった」と述べました。